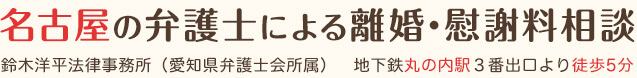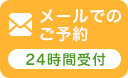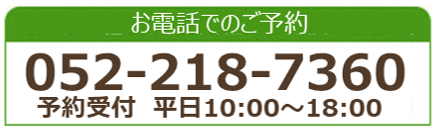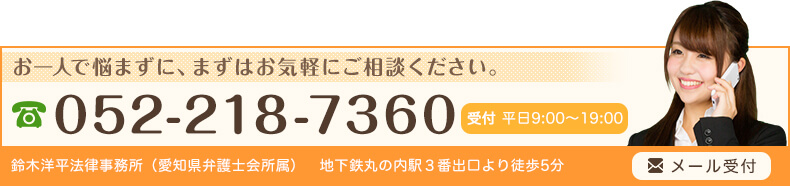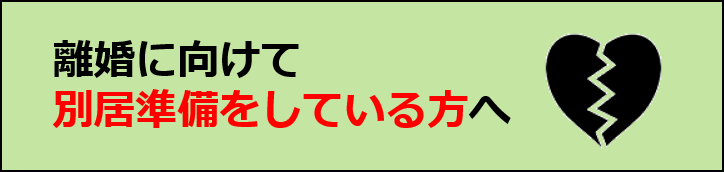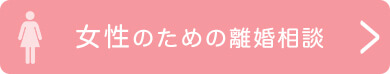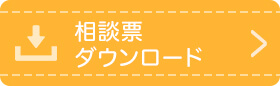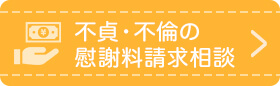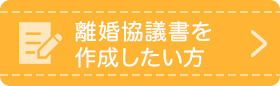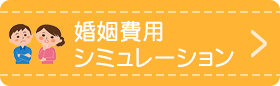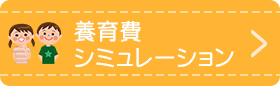共同親権に関するQ&A:お父さん・お母さんが知っておきたい20のこと
目次
はじめに
2026年に施行される改正民法によって、日本でも離婚後に父母がそろって親権を持つ「共同親権」が選べるようになります。
しかし、「共同親権にしたら子どもの生活はどう変わるの?」「親同士が話し合えないときはどうすればいいの?」など、不安や疑問は尽きません。
ここでは、弁護士がよく受けるご相談をもとに、共同親権の仕組みや注意点について「共同親権・単独親権の決定に関するQ&A」「共同親権となったときのQ&A」「その他Q&A」の各項目で解説します。
共同親権・単独親権の決定に関するQ&A
離婚後の親権は共同と単独、どちらが基本ですか?
法律上は、離婚後の親権について「共同親権が原則」「単独親権が原則」という決まりはありません。
裁判所は、ケースごとに子どもの利益を最優先して判断します。
すでに離婚していても、あとから共同親権にできますか?
はい。離婚済みの父母も親権者変更の申し立てが可能です。
裁判所は、父母と子の関係やその他の事情を総合的に見て判断します。
「子の人格を尊重する」とは、子どもの言うとおりにすることですか?
そうではありません。子どもの年齢や発達に応じて意見を尊重しますが、子の利益を守るためには意向に反して制止することも必要です。
その際には「なぜそうするのか」をきちんと伝えることが大切です。
精神的・経済的・性的DV等があれば必ず単独親権になりますか?
必ずではありませんが、「子どもの利益を害する」「話し合いが困難である」と判断されれば単独親権とされます。
養育費を払っていない親でも共同親権を申し立てられますか?
申し立て自体は可能ですが、養育費不払いは不利な事情として裁判所の判断に大きく影響します。
共同親権後に養育費を払わない場合、単独親権に変えられますか?
状況によっては、同居親の単独親権に変更される場合があります。
共同親権となったときのQ&A
共同親権の下では、子を監護している親は、子のことについて、監護していない親の同意を都度取らないといけませんか?
「日常の行為」「急迫の事情」については、単独で決定できます。
ただし考え方が異なる場合は、子どもの利益と父母の協力義務の観点から話し合うことが望まれます。
「生活に大きな影響を与える行為」は父母双方の同意が必要となります。
「日常の行為」とはどんなことですか?
日々の生活に関する行為で、子どもに重大な影響を与えないものです。
たとえば食事や服装、習い事などがこれにあたります。
「急迫の事情」とはどんなことですか?
DVや虐待からの避難、緊急医療、入学手続きの期限が迫る場合など、協議を待つと子どもの利益を害する恐れがある状況です。
子どもの転居は単独で決められますか?
転居は学区が変わらなくても「生活に大きな影響を与える行為」であるため、原則として父母が共同で決める必要があります。
ただし、DVや虐待からの避難など緊急時は単独で可能です。
学校関連の手続きはどうなりますか?
単独で決められること(例:日常の行為)
- 就学時健診の受診、給食手続き、出欠連絡、修学旅行への参加など
共同で決めるべきこと
- 入学・退学・転校・留学・特別支援学校への就学など
学校や病院には親権者の情報はどう伝わりますか?
親権者は戸籍に記録されますが、特定の事項の親権行使者までは記載されません。
実務上は父母の申告などに基づいて判断されるため、事前に説明しておくことが望ましいです。
連絡しても返事がない場合は?
協議を求めても返答がない場合、一定期間を過ぎれば黙示的な同意と評価できることがあります。
緊急時は単独で対応可能です。
DVや虐待がある場合でも共同親権が必要ですか?
無理に協力を強制されることはありません。
共同で親権を行使することが困難な場合は、法律上その協力義務に限界があります。
共同親権下での判断のポイント
共同親権下では,基本的には以下のとおり考えると良いでしょう。そのうえで例外的な事があれば「急迫の事情」も加味した上で判断しましょう。
①「監護及び教育に関する日常の行為」は単独で決定できる。
- 子の生活習慣に関する事項(食事、服装、髪の色、友人関係など)
- 習い事に関する判断(重大な影響を与えない範囲)
- 高校生のアルバイト就労許可
- 学校関連の手続・対応(就学時健康診断、学校給食の申込、出欠連絡・学校行事等の参加同意、三者面談等への対応等)
- 通常の期間内の観光旅行や短期の海外旅行
②「生活に大きな影響を与える行為」は双方合意が必要。
- 子の転居(引っ越し)
- 子の学校に関する重要な手続き(入学・退学・転学・留学・休学就学校変更申立て、特別支援学校就学に関する意見、長期交換留学)
- 子の就職に関する重要な判断(長期勤務先の選択等)
- 子の財産管理に関する判断
- 子の氏の変更・養子縁組(特に15歳未満は父母双方の同意が必要)
その他Q&A
子の扶養義務はいつまで続きますか?
民法上は未成年に限らず、大学生など成年の子に対しても養育費が認められる場合があります。
ただし、必ず支払われるわけではなく、子どもの自立や生活状況などに応じて裁判所が判断します。
共同親権で養子縁組するには?
父母双方の同意が必要です。
成立後は養親が共同親権者となり、もう一方の実親は親権を失います。
執筆者情報

- 鈴木洋平
-
最も大事なこと、それは、お客様と信頼関係を構築すること。
弁護士にしか話せないこと、言えないこともあります。時間をかけても信頼関係を構築することが何より大切だと思っています。話しにくいこと、言いたくないことも出来るだけ話してもらえるよう、私はまずお客様の話す内容を時間をかけて細部までよく聴き、真意をつかみ取るように意識しています。お客様の話す内容については、単にご要望を伺うだけではなく、何故そのような心情に至ったのかを背景事情も踏まえて私なりに分析し、お客様の真意に見合った解決案を提示することを心がけています。
|当事務所の弁護士紹介はこちら
最新の投稿
- 2025.09.11離婚解説共同親権に関するQ&A:お父さん・お母さんが知っておきたい20のこと
- 2025.07.25解決事例離婚後、夫が再婚し再婚相手との子どもが出来たため、元妻に対し養育費の減額請求を行った事案。従前の養育費から月額2万円の減額で合意した例
- 2025.07.23解決事例長期間の別居状態で夫婦間の交流もなかったため、夫の方が離婚の請求をした。 妻は夫からの婚姻費用の継続を求め、婚姻関係はいまだ破綻していないとして離婚に反対。また仮に破綻の場合は、夫の不貞が原因だ(有責配偶者)と主張。最終的には、和解離婚を獲得した例
- 2025.07.21解決事例妻に対して暴言や経済的な依存があり酒癖の悪い夫と離婚したいが、夫が怖くて口論では負けてしまう妻。夫との離婚を強く希望した結果、妻自ら別居に踏み切り、最終的に協議離婚が成立した例